| �`�P�D���������������ꂽ�͍̂�����V�T�N�O�̂P�X�R�O�N�̂��Ƃł��B ���̂����͂Ă̘f���͖��E�̐_�ɂ��Ȃ�Łu�v���[�g�v�Ɩ��Â����܂����B �������͂���܂Řf���Ƃ��ĔF�߂��Ă��܂������A�ŋ߂̋Z�p�̐i�����疻�������ȑO�l�����Ă�������ꡂ��ɏ������V�̂ł��邱�ƁA�C�����ȉ��ɂ������̓V�̂����������悤�ɂȂ�A���ɂ͖����������傫���T�C�Y�̓V�̂����邱�Ƃ��������āA���������f���ł���Ƃ����������h�炢�ł��܂����B �����Ă��ɍ��ۓV���w�A�� (IAU) �ł�2006�N����Ŗ�������f������udwarf planet�v�i���f���j�ւƊi�������邱�Ƃ����肵�܂����B����ɖ������ɂ́A���f���ԍ�134340�Ԃ�����U���܂����B �f���̒�`�͂���܂Ŗ��m�ł͂Ȃ������̂ł����A����̑���Řf���̒�`�����̂悤�Ɍ��肵�܂����B �@1.�@���z�̂܂������]���Ă��邱�ƁB �@2.�@���Ȃ̏d�͂ɂ���ċ��`�ɂȂ�قǏ\���Ȏ��ʂ������Ă��邱�ƁB �@�@�@��薾�m�ɂ����ƁA���Ȃ̏d�͂ɂ��d�͕��t�`��ɂȂ��Ă��邱�ƁB �@3.�@�O����̑��̓V�̂�r�� (clear) ���Ă��邱�ƁB �������̏ꍇ�A3�����Ă��Ȃ��Ƃ������R����f���ł͂Ȃ����f���Ƃ������ނɂȂ����킯�ł��B �܂����z�n�O���V�̓��̐V�����T�u�O���[�v�ł��閻�����^�V�̂ɕ��ނ���܂��B �������ɂ͂܂��f���T���@���K�ꂽ���Ƃ��Ȃ��C�������Ɋւ�����͖]�ɋ���q���ɂ��ϑ��������ɓ����Ă��܂��B ���z�n�̘f���̌��]�O�����قډ~�Ȃ̂ɑ��C�������̋O���͂��ג������~�ł��B ���~�̌`���C�ǂꂭ�炢�~�Ƃ������Ă��邩������킷���l���u���S���v�Ƃ����A���S�����傫���قNjO�����ג����ȉ~�ł��邱�Ƃ������܂��B �n���̌��]�O���̗��S�����O�D�O�Q�Ȃ̂ɑ��C�������̒l�͂O�D�Q�T�ł���A���̒l���f���̒��ōő�ł��鐅���i���S��0�D20�j�����傫���B���������đ��z�ɍł��߂Â��Ƃ��ɂ́C���z����̋����͂��悻�R�O�V���P�ʂƂȂ�C�C��������P���L�������ɂȂ�܂��B����C���z����ł���������Ƃ��ɂ͂T�O�V���P�ʂ̋����ɂȂ�܂��B �܂��f���̋O���ʂ͂قډ����ʏ�ɂ���A�ő�̐����ł��V�x�ł���̂ɑ��āC�������̋O���ʂ͂P�V�x���X���Ă��܂��B �������̌��]�����͂Q�S�W�N�ł���B�P�X�V�X�N�ɊC�����������̋O���ɓ������B �C�����O���̊O�ɏo��̂͂P�X�X�X�N�ł���C����܂ł̊ԁC�������͊C������葾�z�ɋ߂����ƂɂȂ�B �������͂P�X�W�X�N�ɋߓ��_��ʉ߂����B�܂�ł����z�ɋ߂Â��C�n������ϑ����₷���Ȃ��Ă��܂����B ����ɂP�X�W�O�N��ɂ́C�n������݂ĉq���̓����̋O�����������������Ă݂���u�H�v�̔z�u�ɂȂ������Ƃɂ���āC�������̑傫�����͂��߂Ƃ��邳�܂��܂ȃf�[�^�������܂����B |
| �������Ɖq���J���� |
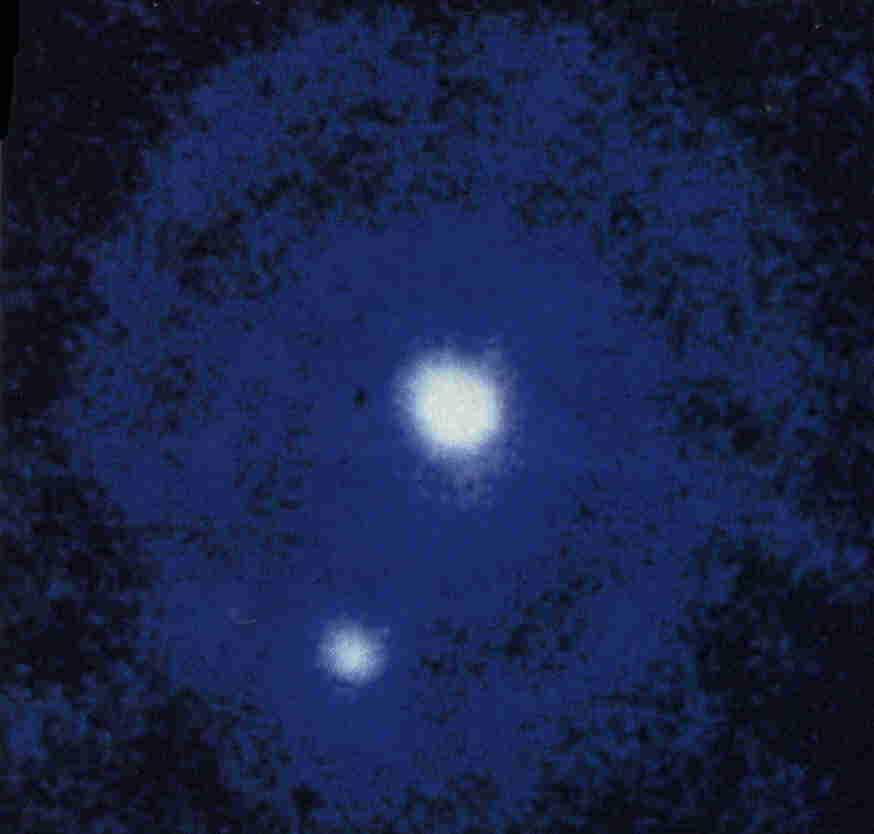 |
�@�������̊�{�f�[�^
| �O�������a �i�V���P�ʁj |
���]���� �i�N�j |
���]���� �i���j |
�ԓ����a �ikm)�j |
���� �i�n�����P�j |
���ϖ��x �ikg�^�u�j |
�\�ʏd�� �i�n�����P�j |
�q���� �@ |
| �R�X�D�T�S | �Q�S�V�D�W�O | �U�D�R�W�V�i�t�s�j | �P�P�R�V | �O�D�O�O�Q�Q | �Q�P�R�O | �O�D�O�V | �R |
| �`�Q�D�������̉q���̓����͂P�X�V�W�N�ɔ�������܂����B����Ƀj�N�X�ƃq�h���̂Q�̉q�����Q�O�O�T�N�ɔ�������A�������̉q���͂R���m�F����Ă��܂��B �J�����̋O���𑪒肷�邱�Ƃɂ��C�������Ɨ̓����̋����������w��߂����Ƃ��킩��܂����B �ŋ߂̕ł́C���̋����͂P�X�C�U�S�O�L���O��Ƃ���Ă��܂��B �n���̌����C�n�����a�̖�U�O�{�i��R�W���L���j�̋O�������]���Ă���̂ɂ���x�āC�̓����͖��������a�̖�P�V�{�Ƃ������ɋ߂��O�������]���Ă��܂��B �������ƃJ�����̂悤�ɁC����قǐڋ߂�����̓V�̂̊Ԃɂ͋��������͂������܂��B ���̂��߃J�����̋O���͂قډ~�ɂȂ�C�������̎��]�ƁC�J�����̌��]�E���]�͓������Ă��܂��B �������̎��]���̌X���͂P�Q�Q�x�ŁC���]�����͖�U�D�S���ł��B �H��������ƁC�������ƃJ�����̑S�̖̂��邳�́C�H�ł������ꂽ�ʐς̕������Â��Ȃ�܂��B �����Ō��̋��x�����ԂƂƂ��ɕω�����悤���x��ƁC�������C�J�������ꂼ��̑傫�����킩��܂��B �������̐ԓ����a�͂Q�R�O�O�L���C�J�����̒��a�͖������̖��̂P�Q�O�O�L���ł��B �������́C�n���̌��̖�R���̂Q�C�ő�̏��f���ł���Z���X�̂Q�D�T�{�ɂ������Ȃ��傫����������܂���B �܂��������ɑ���J�����̑傫���́C�q���Ƃ��Ă͔��ɑ傫���A�������ƃJ�����͘f���Ɖq���Ƃ������C�����I�ɂ͘A���n�Ƃ����܂��B �P�X�X�P�N�ɂ́A�n�b�u���F���]�����Ŗ������ƃJ�����̉摜���B���܂����B ���݂̂Ƃ���A�J�����̂ق��ɂ͉q���݂͂����Ă��܂���B �J�����̎��]�ƋO���^���͓������Ă���A���傤�nj������������ʂ�n���ɂނ��Ă���悤�ɁA��ɖ������ɓ����ʂ��ނ��Ȃ��炻�̎��͂��܂���Ă��܂��B�܂��������̎��]���J�����̋O���^���Ɠ������Ă���A�������͏�ɓ����ʂ��J�����Ɍ����Ă��܂��B ���ϖ��x�͂P�������[�g��������Q�P�R�O�L���ƂȂ�C�����̓V�̂��X�̂ق��Ɋ�Ύ����������Ȃ�܂ނ��Ƃ������Ă��܂��B �ŋ߂ł͖������ƃJ���������邱�Ƃɂ��A���߂Ă���]�����ɂ��J���������̐ԊO���X�y�N�g�����ϑ����邱�Ƃɐ������܂����B ���̌��ʁA�J�����̕\�ʂɕX�����݂��邱�Ƃ��m�F����܂����B �ʔ������ƂɁA�������̃X�y�N�g���ɂ͕X�̋z���͂Ȃ��A�܂��t�ɖ������̃X�y�N�g���Ɍ����Ă��郁�^��(�ő�)�Ȃǂɓ����I�ȋz�����J�����ɂ͌���ꂸ�A���V�̂ŕ\�ʑg�����傫���قȂ��Ă��邱�Ƃ�������܂����B �Q�O�O�T�N�ɂ̓n�b�u���F���]�����̊ϑ��ɂ��A����ɂQ�̉q������������A���ꂼ��A�j�N�X�A�q�h���Ɩ�������܂����B�����̓J�����ɔ�ׂ�Aꡂ��ɏ������V�̂ŁA���̓����͂قƂ�ǂ킩���Ă��܂���B |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�`�R�D�������́C���傤�ǃg���g���̂悤�ȕX�q���Ɠ��l�̐����������Ă��āA�ł��\�ʂ������A�����Ȃ������C�������Ă��܂��B
�������̓K�X�̘f���ł͂Ȃ��C�n���Ɠ����悤�Ȍő̂̕\�ʂ������Ă��܂��B
����ɖ������ɂ͔��ɔ�����C�����݂��Ă��܂��B����͖������������������u�P���H�v�Ƃ������ۂɂ���Ċm���߂��܂����B
�P�����������ɂ��������Ƃ��ɁC�P���̌��������ɂ݂��Ȃ��Ȃ�̂ł͂Ȃ��C�������ƖŌ������̂��؋��ƂȂ�܂����B
�����̂���������C�������̑�C�͓����ȏ�w��C�ƁC���Ȃ�s�����ȉ��w��C�ɁC�͂�����ƕ������邱�Ƃ��킩���Ă��܂��B
�������\�ʂł̑�C���̓g���g���Ɠ��l�Œn���̂P�O�����̂P�ł��B
�X�N�g���ϑ�����C�������̓��^���̕X�܂��͑��ŁC�̓����͐��̑��ł������Ă��邱�Ƃ��킩��܂����B
�X��̃��^���̏��C���͉��x�ɂ���߂ĕq���ł���B
�h�q�`�r�i�ԊO���ϑ��q���j�̊ϑ����猈�肳�ꂽ�������̕\�ʉ��x�̓}�C�i�X�Q�P�T���ŁC���^���̑�C�����݉\�ȏ����ɂȂ��Ă��܂��B
�������̃A���׃h�i���˔\�j�͑傫���C���悻�T�O���ł��B
����́C�\�ʂ𖾂邢���^���̕X�ł������Ă��邽�߂ł���ƍl�����܂��B
���������^���̕X�͒����ԑ��z�̎��O������ː��ɂ��炳���ƈÂ����̂ɕω����܂��B
�����������z���牓�������ĕ\�ʂ̉��x��������Ƒ�C���̃��^�����Ïk���C�n�\�ɐV��Ƃ��Đς���̂�������܂���B
�������́C�C�����ő�̉q���ł���g���g���ɁC�傫���▧�x�C������C�����_���悭���Ă��܂��B
���������āC�������ƃg���g���̋N���ɂ��ẮC�����悤�ȉߒ����o�Č`�����ꂽ�V�̂��C����͊C�����ɂƂ炦���ĊC�������܂��q���ƂȂ�C�����[���͑��z�����]����悤�ɂȂ����Ƃ�������������܂��B�J�����̋N�����Ȃ��ł��B
�������̓K�X�̘f���ł͂Ȃ��C�n���Ɠ����悤�Ȍő̂̕\�ʂ������Ă��܂��B
����ɖ������ɂ͔��ɔ�����C�����݂��Ă��܂��B����͖������������������u�P���H�v�Ƃ������ۂɂ���Ċm���߂��܂����B
�P�����������ɂ��������Ƃ��ɁC�P���̌��������ɂ݂��Ȃ��Ȃ�̂ł͂Ȃ��C�������ƖŌ������̂��؋��ƂȂ�܂����B
�����̂���������C�������̑�C�͓����ȏ�w��C�ƁC���Ȃ�s�����ȉ��w��C�ɁC�͂�����ƕ������邱�Ƃ��킩���Ă��܂��B
�������\�ʂł̑�C���̓g���g���Ɠ��l�Œn���̂P�O�����̂P�ł��B
�X�N�g���ϑ�����C�������̓��^���̕X�܂��͑��ŁC�̓����͐��̑��ł������Ă��邱�Ƃ��킩��܂����B
�X��̃��^���̏��C���͉��x�ɂ���߂ĕq���ł���B
�h�q�`�r�i�ԊO���ϑ��q���j�̊ϑ����猈�肳�ꂽ�������̕\�ʉ��x�̓}�C�i�X�Q�P�T���ŁC���^���̑�C�����݉\�ȏ����ɂȂ��Ă��܂��B
�������̃A���׃h�i���˔\�j�͑傫���C���悻�T�O���ł��B
����́C�\�ʂ𖾂邢���^���̕X�ł������Ă��邽�߂ł���ƍl�����܂��B
���������^���̕X�͒����ԑ��z�̎��O������ː��ɂ��炳���ƈÂ����̂ɕω����܂��B
�����������z���牓�������ĕ\�ʂ̉��x��������Ƒ�C���̃��^�����Ïk���C�n�\�ɐV��Ƃ��Đς���̂�������܂���B
�������́C�C�����ő�̉q���ł���g���g���ɁC�傫���▧�x�C������C�����_���悭���Ă��܂��B
���������āC�������ƃg���g���̋N���ɂ��ẮC�����悤�ȉߒ����o�Č`�����ꂽ�V�̂��C����͊C�����ɂƂ炦���ĊC�������܂��q���ƂȂ�C�����[���͑��z�����]����悤�ɂȂ����Ƃ�������������܂��B�J�����̋N�����Ȃ��ł��B